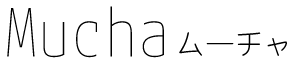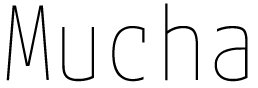みなさんは仏像はお好きでしょうか。
わたしは時間が合うと仏像展に行くのですが、できれば自分でも彫ってみたいと思っていました。
そしていただいたのがこちら。
かわいいお地蔵さまが彫れるもの。
今回はこちらをつくってみたいと思います。
(このセットは発売元の道刃物工業さんでは、今はお取り扱いがないようですが、MonotaRoさんでは販売されていました。2023年1月時点)
セット内容と必要な道具
- ・小細工のみ(21mm)
- ・彫刻刀(10本)
-
- 平刀(6mm/10mm)
- 丸刀(3mm/4.5mm)
- 印刀(6mm/12mm)
- 浅丸(7.5mm/9mm/12mm)
- 三角刀(6mm)
- ・加工材(ヒノキ/68×58×150mm)
- ・作業台
- ・布製彫刻刀入れ
- ・つくりかた書籍「らくらく彫れるかわいいお地蔵さま」
こちらがセットになっています。
彫刻刀だけでも10本入っているなんて、お得な気分になります。
ヒノキの加工材は単品でも購入できるとのことなので、失敗してもまた挑戦できますね。笑
これ以外に必要なものは
- ・定規
- ・えんぴつ
- ・のこぎり(工作用の小さめがおすすめ)
- ・ブラシ(削り屑を取り除く用)
- ・手鏡(お顔の左右が同じかチェックするため)
です。
定規は狂いの少ない金属の定規や直角を確認するためのスコヤ、凹凸がある部分に線を描くための柔らかいプラスチック定規があるとよいです。
制作開始!何をつくるか
教本には、「半面地蔵」、ふたり並んだ「仲良し地蔵」、「丸彫りのお地蔵さま」、「かわいい観音さま」の彫り方と図案が載っています。
セットの加工材が丸彫りのお地蔵さまのサイズでしたので、こちらをつくります。
荒落とし
セットのヒノキにはあらかじめ首、足の部分に切り込みが入っています。
企業様のやさしさですね。
まずは木材に中心線を引き、そこに図面を見ながら大きく切り落とす部分を書き込み、のこぎりで切り落としていきます。(教本通りに順番に落としましょう。)
中心線は大事なものですので、途中で消えたらまた書き直しします。
角の部分を深く切りすぎないように注意しながら進めています。
のこぎりは慣れている方だと思っていましたが、卓上で切るのは力の入れ具合が難しい・・・やたら時間がかかります。
のこぎり跡や角の部分の落とし残しを彫刻刀の浅丸刀、もしくは平刀で落としてきれいにしてから、教本の指示通り、次の箇所をまた落としていきます。
ざっくりと余分な部分を落としたら、次は角を落としていく工程です。
(工程上はまだ荒落としですが、ちょっとわくわくしてきました。)
のこぎりで落としていくということでしたが、作業も夜中になってしまっていたので、騒音を考え、浅丸刀と平刀で落としています。
そして、やっと荒落とし完了。
思っていた以上に結構な時間がかかり、疲れました。
でもこれから形になっていくことを考えると、手を止めてはいられません。
デザインを写す
本来であれば「トースカン」という工具を使って図面を写すとのことなのですが、用意しているはずもないので、図面を参照して中心線や頭の天辺、底からの長さを図り、手書きで写していきました。
お顔がつくと、よりイメージがつかめますね。
全体を丸く
いよいよ、といきなり眼や鼻から行きたくなりますが、まずは
- ①耳を出す(耳の周りを彫る)
- ②その彫った部分に合わせて周りを彫りながら、頭を丸く整える
- ③その流れで身体も丸めていく
という工程を行っていきます。
緊張しますね。
わたしの地蔵さまは、生真面目にもラインぎりぎりに彫ったため、あとになってどんどん耳が小さくなってしまいました・・・。
この段階では耳は割と大きく余白を取っておいたほうがよいです。
顔をつくる
- ①鼻の下のラインを入れ、そこから顎まで1段彫りさげる
- ②鼻〜眉を彫り出す
- ③眼を彫る
- ④まぶた、ほっぺたの角を取る
- ⑤口を彫り出す
という工程なのですが、教本でも写真付きで説明していただいているのですが・・・、よくわからない・・・。
この段階では。
あとになって、より細部を彫る段階で、この時点でやっておけばいいのか。となんとなくわかった感じです。
あとはどれだけ深く彫ればいいのか、浅いほうがいいのか?
というのがわかりませんでした。
なので、すべて恐る恐る。笑
とにかく、わからないながらも進めます。